ヤコブ書の第一章を中心に、二、三回の予定で、試練に関してのヤコブの教訓をお話ししたいと思います。
まずこの書の著者でありますが、聖書にはヤコブという名が三つ出ております。
(一)は「ゼベダイの子ヤコブ」で、使徒ヨハネの兄弟でありました。ヨハネと共に早くから使徒に選ばれ、イエスの最も親しい三弟子の一人でありましたが、紀元四十四年に、ヘロデの命により斬首されました。『使徒行伝』十二章一、二節に、「その頃ヘロデ王、教會のうちの或人どもを苦しめんとして手を下し、をもてヨハネの兄弟ヤコブを殺せり」とあるのがそれです。
(二)は「アルパヨの子ヤコブ」で、この人の名はマタイ伝十三章三節に見えており、彼もまた十二使徒の一人でありましたが、事跡はあまり明らかではありません。
(三)は「主の兄弟ヤコブ」であって、これがすなわち本書の著者であります。マルコ伝六章三節に、「の人(=イエス・キリスト)は(=大工)にして、マリヤの子、またヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ならずや。の姉妹もに我らと共におるにずや」とあります。彼はイエスの兄弟であり、かつ非常に高徳の人であったため、自然にされてエルサレム教会の会長のごとき立場にありました。
一般信者から尊信を受けたことはもとより、ペテロ、パウロのごとき使徒たちからもされました。ペテロが獄をれた時にも、またパウロが第三次伝道からエルサレムに帰った時にも、まずこのヤコブに報告に行っているのを見ても、その間の消息(=事情)を推知することができます。
ヤコブは厚重の人でした。キリストの道を信じましたが、ユダヤの古礼・習慣のうち、るべきものは採ってこれを守りましたから、キリストの道を信じない一般のユダヤ人さえも、「しきヤコブ」と称えて尊敬したということです。
彼もまたユダヤ人の指導に心を注ぎ、始終エルサレムに留まって伝道に努めたのでありましたが、(=[ユダヤの]総督)フェストの死後、悪しき祭司長が多くの悪漢をして、彼を宮の庭に引き出してしました。紀元六十二、三年の頃の事でありました。
『ヤコブ書』は、新約聖書の中でも早期に世に出たものではなかろうかと言われております。すなわちその内容に、「異邦の信者」に言及したところがありませんから、パウロが異邦に伝道して、《割礼》が問題とされるに至る以前のもので、おそらく紀元四十五年頃のものであろうかと思われるのであります。
序論はこれくらいにとどめて、これから本題に入ってお話しすることに致します。
(第一)挨拶
「神および主イエス・キリストのヤコブ、散り居る十二のの平安を祈る」(1-1)。「神」と「主イエス・キリスト」と語は二つになっておりますが、ヤコブの心中においては、この二つはまさに一つであります。キリストは人となった神であり、神の本質はキリストによって知られるのであります。神と言えばキリスト、キリストと言えば神、そうなるのが深い信仰であります。
ヤコブは係累上、キリストの兄弟でありましたが、そういう事に必要以上にわれて、キリストを尊称することを遠慮したり、また逆に血縁を誇ったりするようなことはありませんでした。それは(=親族関係)以上の信仰の関係、何ものにも捉われぬ道の関係がわかっていたからであります。
そして自分は神とキリストとのであると公言していたのであります。先生は「自分はキリストの志願奴隷である」と言っておられました。奴隷には己の意志というものはありません。全く我意・私情なしに神とキリストに隷属する、それこそ忠実の信仰であります。
「散り居る十二の族の平安を祈る」。普通の手紙の挨拶と言えば、暑いとか寒いとか、暮らしに変わりはないかとか、平凡な話題を並べるのが常であります。私が昔、勤務していた埼玉県の熊谷という所は、冬の季節風が非常に強い土地でありましたので、「今日は静かですね」と言うのが朝の挨拶になっておりました。
「平安を祈る(=「シャローム」)」とヤコブがここに言ったのは、一見、当りりのない挨拶文にも見えますが、実際に相手の心身両面の安否を気遣う心にちていて、極めて情のもった言葉となっております。
その昔、ヤコブ(=イサクの子)には十二子があり、それが分かれて十二のユダヤ部族となりました。ユダヤはたびたび外敵の侵攻を受け、時には国民大半が捕虜となって遠国にされたこともありました(=バビロン捕囚)。また商才にけていて、遠く外国にまで出稼ぎに行く者もあり、キリストの時代にはバビロニア・小アジア・シリア・ギリシア・ローマ・エジプトなど、各地に散在しておりました。そしてまだキリスト教が公認されていない時代ですから、さまざまな困難があり、迫害もあり、心労も多かったのであります。それでヤコブは、まずその《平安》を祈ったのであります。「山を隔てて煙を見、早くもこれ火なるを知り、(=垣根)を隔ててを見、ちこれ牛なるを知る」(碧巌録)。最初のちょっとした挨拶の中に、すでにヤコブの信仰と修養と愛とが現れているのであります。
(第二)忍耐・歓喜
「忍耐をしてき活動をなさしめよ」(1-4)。
忍耐がいかほど大切なものかは、『大集経』という経文の中に、「世にむ(=頼りにする)所なし、ただかののみ恃むべし。忍は(=安全な住い)なり、(は)生ぜず。忍は(=丈夫な)なり、(を)加えず(=衛兵を増やす必要がない)。忍は(=巨船)なり、て難を渡る(=困難を乗り切る)べし。ゆえに諸仏(は)常に忍をす(=える)」とあります。
人は非常な困難の中にあっては、才も智も力も何の頼りにもならない。もし何事かにって、それで切り抜けられるくらいなら、まだ真の困難ではないのであります。
何も頼るべき物がなくなった時、ただ一つ残されたものが忍耐であります。この忍耐のに身を寄せれば、困難の暴風雨も害なく通り過ぎ、この忍耐のをえば、(=多数の敵)も危害を加え得ず、忍耐の大舟に乗れば、安全に難を渡ることができるのであります。
しかしながら、ただ苦通を我慢するというのでは、苦しいばかりで長続きしません。ゆえに、「なんぢらのにふとき、これをとせよ」(1-2)と説いて、古人のいわゆる「苦中にをする」(言志)を教えたのであります。ただしこれを実行するに当たっては、二つばかり肝要な条件があります。
(イ)感謝して神の教育を受けるという信仰であります。の中に神の教育を受ける。これはパウロなども体験した事であります。いわく「のみならず患難をも喜ぶ、そは患難は忍耐を生じ、忍耐は練達を生じ、練達は希望を生ずと知ればなり」(ロマ5-3)。患難の外形に捕われず、その内に入って、神のご教育を受けて修行していけば、パウロの体験したような体験を私どもも得ることができるのであります。
(ロ)究極の目標を見失わないこと。神のしはどこにるか。「天の父のきが如く全かれ」(マタイ5-48)というのが神のであります。神が患難を与え給うのも、この患難を通じて我々の足らざる所を自覚反省せしめて、我々の信仰を進め、我々の人格を一層完全ならしめんとの思召しであります。それを知れば、困難だからとて道を離れたり、横道にれたりするものではありません。
(第三)反省向上
患難にわぬと、人は(内を省みずに)外ばかりを見、対外的事業に熱中します。セント・ヘレナのナポレオンがそうでした。彼は戦い敗れて絶海の孤島に流された時、今まで外にばかり向けていた心を己に向けて、自身の失敗の原因を反省し、「人があまり順調に成功することはって不幸である。自分は早々に出世したため、知らず知らず傲慢になっていた」と気づきました。そして己の人格と事業をキリストのそれと比較して、自分はとても及ばないと知り、そっと聖書に手を置き、「人もしこの書に従って歩むなら、恐らくを誤ることはなかろう」とつぶやいたと言います。
「汝らのもし智慧のくる者あらば、むることなく、また惜しむ事なく、ての人にふる神に求むべし。らば與へられん」(1-5)
孟子は「なうて得ざるものあれば、を己にす(=物事が上手く行かぬ時は、まず自身を反省する)」(孟子・離婁上)と言いました。私の父(=開祖先生)はさらに加えて、「己に反求して足らざるものは、これを神にせよ」と言いました。この「神に上求する」というところは、ヤコブが「神に求むべし」と言ったのと同じです。
人が実際に変わろうとする時には、ただ変わろうと思うだけではなく、よほど一生懸命にならねばならぬことを悟ります。それが反省と向上です。そうなった次には、
(第四)超越聖化
人は人格が低いと低いものに捉われ、小さいと小さいものに固着します。しかし患難に遭うことによって、消極的には忍耐し、積極的には反省向上して、高く、大きく、深くなって行けば、低いこと・小さいこと・浅薄なことを超越し、患難など物ともしなくなるのです。
「き兄弟は、おのれが高くせられたるを喜べ、富める者は、おのが卑くせられたるを喜べ」(1-9)。身分が高くなったとか低くなったとか、富を得たとか失ったとか、そういう関心の段階を超越してしまうのです。人は道そのものを楽しむ精神を持たねばなりません。そうでないと、道をも己に利用しようとします。そんなことでは、真に道を修めることなどできるものではありません。
「そは草の花のごとく、過ぎゆくべければなり。日で熱き風吹きて草を枯らせば、花落ちて、そのしき姿ほろぶ、富める者もまたのごとく、そののにしてまづせん」(1-9~11)
この世のの(=極めて短い)生活に現れて来るいろいろの欲望に捉われず、永遠への行程としてこのを過ごす。こうして全てを道にいて使うことができるのであります。く、「えいかなるわしき事ありとも夢になして(=現実とはさずに)、ただ法華経の事のみ、さはぐらせ(=考える)給うべし」(兄弟抄)と。「英雄をせばち神仙(=現世的な英雄にも、ふと仙境に遊ぶ時がある)」(黄天谷)、あの豪傑僧(=日蓮)にも、こんな超越した境地があったのかと、非常に奥ゆかしく感ずる次第であります。
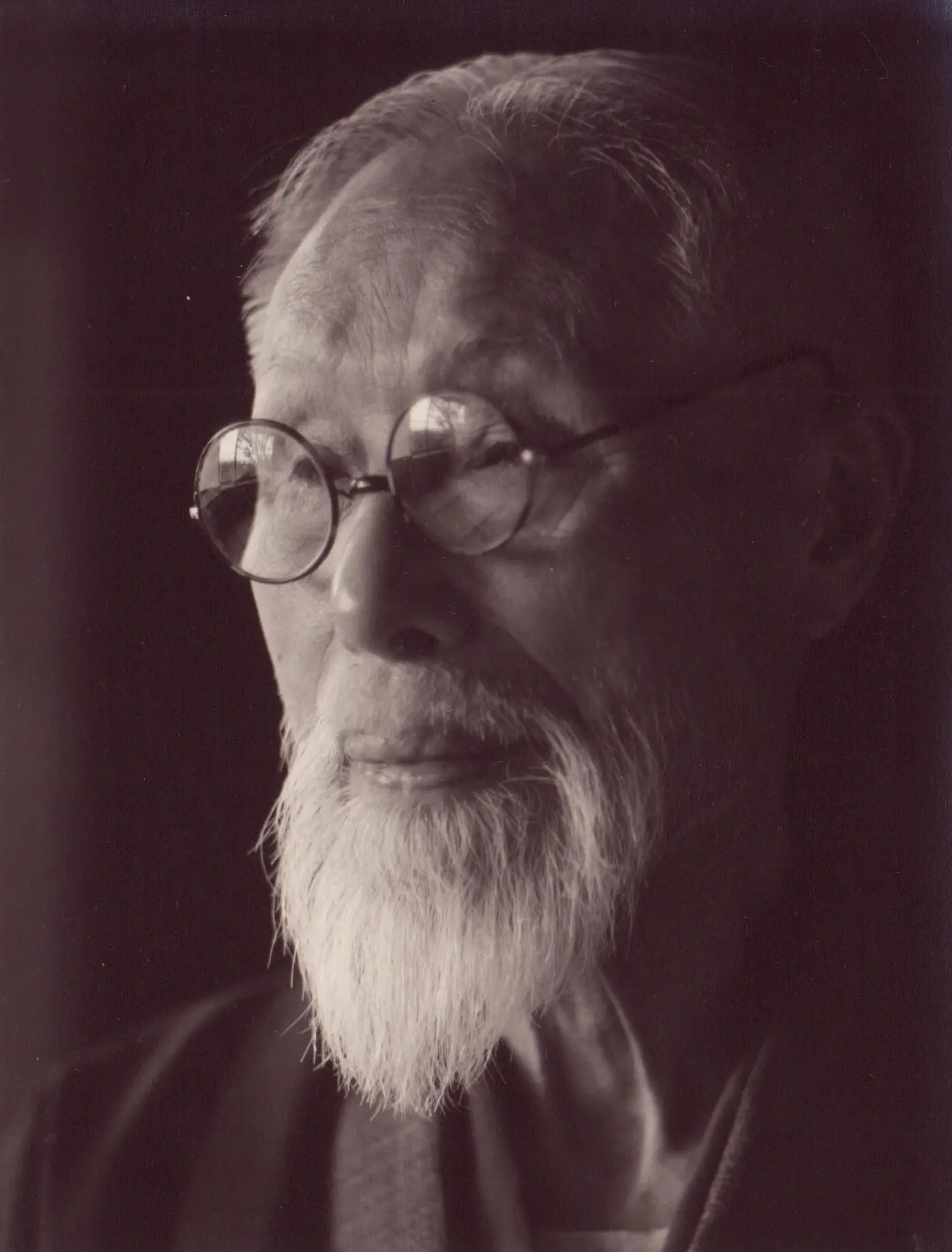

コメント