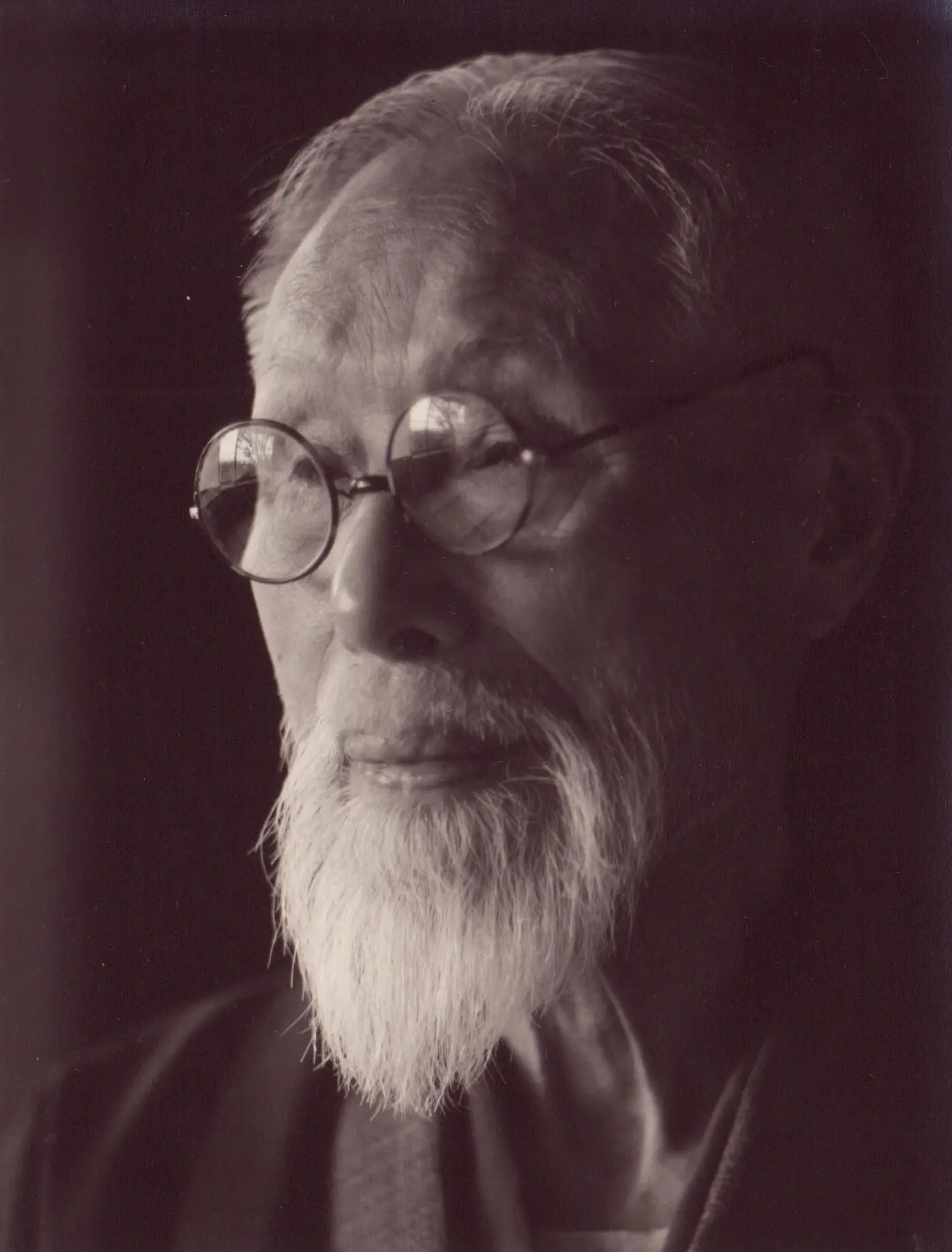大正十三年十一月十九日
於大阪毎日新聞社
諸君もお聞きになったでしょうが、欧州戦争(=第一次世界大戦)の時、英国では戦場に出た男子に代わって婦人が外に出て働いた。すると週に三十円(=約9万円)の賃金が得られた。ところが戦争が終わって夫が帰って来て、婦人が家で仕事をすると、週に十円しか得られない。差額の二十円を細君(=妻)は夫に請求できると論じた学者があった。夫婦の間でそんなことを争ってどうしますか。
キリストは「愼みて凡ての慳貪をふせげ、人の生命は所有の豐なるには因らぬなり」(ルカ12-15)とお教えになり、続いて意味深い譬話をなさいました。曰く「ある富める人が、自分の田畑がよく実ったので、今ある小さい倉を壊して大きな倉を立て、自分の作物と財産を全てそこにしまっておこうと考えた。そして自分の魂に向かって、『多年安楽に過ごすべき多くの善き物を蓄えたゆえ、安心して飲み食いせよ』と語りかけようとしたその時、神が言われた。『愚かなる者よ、今宵なんぢの靈魂とらるべし。然らば汝の備へたる物は誰がものとなるべきぞ』。およそ自分のために蓄財し、神に対して積まぬ者はこうなる」(同16~21)と。
この真理と事実に照らしてみれば、資本家の貪欲も労働者の我欲も、ともに憐れむべきものであることがわかります。そんなものを互いに奪い合おうとするのは、何と浅ましいことかと思わずにはおられません。これについては十六年間、実地に当って研究してまいりましたから、いろいろ申し上げたいことはありますけれども、時間がなくてお話しできません。
かつて私どもが教わった経済学では、「最小の労力でもって、最大の利益を得るべし」とありましたが、今日この定義を曲解して、「なるたけ働かずに、たくさん(金を)取るのが利口」と考える横着者がおります。そこでこれを変えて、「正当の勤労を尽して、正当の利益を得るべし」としたらよいと思います。制度や組織の改革も必要ですが、それだけで世界は幸福にはなりません。信念を改め、思想を改めていかねば、今の世界を救うことはできないのであります。
諸君もご承知のラッセル(=20世紀英国の哲学者)なども、「人に所有欲のある限り、争いは止まぬ。むしろ人は創造欲をもって生きねばならぬ」と論じています。しかし私は宗教の方面から考えて、面白い事を発見しました。逆に人間の所有欲を出来るだけ大きくして、小さい所有欲を超越してしまったらどうか。釈迦は「この三界(=一切衆生が輪廻する三種の世界。欲界・色界・無色界)は全て我が所有なり。その中の衆生は全て我が子なり」(法華経)と言っています。少しの物を私有しようとするから取り合いになる。世界全部が自分のものだと思えば、小さな欲など消し飛んでしまいます。キリストも、「父は萬物を我が手に委ね給へり」(ヨハネ13-3)と言われました。釈迦とキリストの二大聖人が異口同音に言ったばかりか、使徒パウロもまた、「何も有たぬ者の如くなれども凡ての物を有てり」(コリント後6-10)と言っております。
昔の人ならいざ知らず、今時そんな気宇(=心の広さ)壮大な考えを持っている人は稀でありましょうが、少なくともこの私は持っています。ですからどんな地位の高い人であれ、お大尽(=金持)であれ、大企業の社長であれ、ちゃんと教えることができます。この絶大の境地から見れば、何億の金も大臣の椅子も何物でもない。道というものには、地位にも金銭にも代えられぬ尊い大きいものがあり、精神を修めていけば誰でもそこに達する事ができるのです。一国の総理大臣は一人と決まっていて、誰でもなるわけにはいきませんが、無限大の境に入り、天地を所有し、物外(=物欲の外)に超越していく道は、誰の前にも広く開かれている。諸君とてその気になれば、いつでも入っていくことができるのです。
話が少々逸れましたが、とにかく労働の精神を自己の利欲の上に置くことは不健全であります。不健全であるから、上下の間に亀裂を生じたり、労使に紛争が起こったり、怠惰の気風を長じたりして、思うほどの利益は上がらない。
またようやく金が手に入ったとしても、人の慾望は際限ないものであるから、さらに金が欲しくなって、不法手段に訴えたり、不人情に走る者さえ出て来る。またせっかく得たその金を、あたら(=惜しいことに)酒食に費やしたり、賭博に投じて摩ってしまったり、あるいは成金風を吹かせて乱費したり、金に物を言わせて名誉の地位を買い取ろうとする者も出て来る。このように金銭というものは、人に真正の満足と安心を与えるには、ほど遠いものであることは明らかであります。
次に、労働の精神を己の名誉の上に置くとどうなるか。先にも申したとおり、財産ができると今度は名誉が欲しくなる。アメリカは世界の成金国でありますが、アメリカ人が金持になると、英国の貴族と結婚したがる。日本でも金ができると爵位が欲しくなり、華族と婚姻関係を結びたがる者があります。
労働の目的をそんな所に置くとどうなるか。これまた多々弊害を伴うものであります。名誉を争う結果、嫉妬心が起こります。中国の昔、鄭の荘公という人があり、その下に考叔という忠臣があり、大変信任を受けておりました。ある時、公に從って許に攻め入り、敵城に一番に乗り込みました。ところが同じ味方の公孫子都というものがこれを見て嫉妬の念に駆られ、密かに背後から矢を放って射殺してしまいました。嫉妬も甚だしくなるとこういうことになります。そんなものに労働の意義を託するのは賢明とは言えません。
いわんや酒色のため、あるいは賭博のためとなってしまっては、堕落の極みと言わざるを得ません。
ではどういう精神で労働したらよいか。それは《天職を果たす》という精神、約めれば《職分》という観念(=考え)で働くことだと思います。《職分》という考えは西欧では非常に発達している徳であります。私はかつてこの問題についていろいろ調べた最後に、東洋の書物に目を転じましたところ、ようやく諸葛孔明(=劉備玄徳麾下の智将)の「出師表」(=出兵を上奏する文章)の中にこの二文字があるのを発見して非常に嬉しく思ったのでした。「此れ臣の(=臣下たるこの私が)先帝(=劉備)に報じて陛下(=先帝の遺児・劉禅)に忠なる所以(=理由)の職分なり」とあります。職分という観念は、ごく古くから東洋のああいう偉人の心の中に根付いていたものが、だんだん忘れられて、近頃西洋から逆輸入されてやっと気が付いたというわけです。
西洋においては、諸君ご承知のジョージ・ワシントン(=米国初代大統領)などは、この職分の念をもって生涯を一貫した人です。その他、英国の名将ウエリントン(=ナポレオンをワーテルローに破った英国の将軍)、あるいはネルソン(=ナポレオン艦隊を撃滅した英国の提督)のごときもまたそうであります。ネルソンはトラファルガー沖の海戦に大勝利を収めましたが、自らも敵弾に倒れ、まさに息を引き取らんとする時、「神に感謝す、我は職分を尽したり」と言いました。
今どき《職分》などと言うと、「そんな七面倒臭い事を考えていては、利益が上がらぬ、名誉にあり付けぬ」と言う人がいるかも知れませんが、そういう人に対して私は質問します。「利益や名誉の正体をわかっておられるか」と。すると大概、答えに窮してしまう。そこで私は説明する。「名誉・利益は実体のない影に過ぎない」と。そんな空しい影を追って粉骨砕身する。私の友人などにも相当有名になっている人がありますが、人気者はその名声を維持しようと大変な苦労をしています。けれどもせいぜい数年で世間から忘れられてしまうのです。
また新聞・雑誌などでご覧になっているでしょうが、流行児というものはだんだんに変わっていきます。初めは一生懸命勉強して世間に打って出るのですが、一たび有名になるや、その名誉を維持しようと、自分の持つ十の知識を、十五にも二十にも誇張して発表する。そして種切れにならぬよう、新しい西洋の雑誌や新刊書を絶え間なく読む。落ち着いて考えたり、深く修めたり、自ら実行しているような暇はありません。その骨折りたるや、実に気の毒なくらいであります。
世間の評判など空しい影に過ぎないのであって、己の本体を養い、実体を善くしていけば、影も自ずから善くなり、名声は勝手に付随してきます。名誉を思わず、利益を考えず、神の前に人格を修め、職分を尊重して忠実に努めていけば、名誉は後から随いてくる。要らないと言っても勝手に随いてきます。それがわかれば、影を追う愚かしさが知られます。
職分の観念が内に確立した時、事業家・労働者の心に正しい安定が生まれます。それはちょうど夜空を見上げると、北極星が北の方に座を占めて、群星が燦然とそれを取り囲んでいるようなものです。各々その職務を忠実に果たしていけば、名誉や利益などは影のように付き従って来るのです。それを本末転倒して、ひたすら影を追って、あたら(=もったいないことに)人生を迷ったまま終わってしまう。
この職分の観念が各個人に徹底しますと、国民として卓越したものが生まれます。先般の欧州戦争の最中、英国の兵器工場を視察に行った人があります。当時は日英同盟の関係がありましたから、日本人は歓迎されて、有名な十六吋(=口径40㎝)砲の工場も見せてもらった。ところがそこで働いているのは職工だけで、監督が一人もいない。そこへ日本人が入って行っても、誰一人好奇の眼を向ける者もなく、粛々と勤務している。そこで歩を進めて、四十歳くらいの職工に、「この工場の監督は誰か」と聞いてみた。すると彼は直ちに答えて、「監督は我が職分」と言った。「では職分の監督は誰か」と聞くと、隣にいた二十歳くらいの職工が、「監督は我が良心」と答えたという。自分の良心そのものが監督であるから、わざわざ監督官を置く必要はないということです。「なるほど、英国が世界一富強であるのは、国民にこういう精神があるからである」と納得したそうです。
こういう精神で勤労していくと、労働の中に《信仰・修養》の念が入って来ます。私どもの工場(グンゼ)でも、上から下まで職分の精神を重んじて働いております。しかも一番よく働いているのは社長・専務・工場長らでありますから、行員が上司を羨むなどということは少しもありません。上下、心を一つにして働くことによって、人格が高まり、働きが純一になり、製品が善くなります。こうして所謂「売って喜び、買って喜ぶ」という、商法の理想が実現されるのです。
(社外の)養蚕農家に対しても同様で、会社から指導員を派遣して技術の向上を図るとともに、一家の気風を善くするよう指導し、できた繭は正当な値段で買い取って、「正当な勤労は正当な利益を生む」ことを実地に示し、「家長の人格が修まり、一家和合して働く家が、最も善い繭を作り、結果、最も多くの利益を得る」ことを示すのであります。