基督心宗教団発行 基督の心第三〇七集より
学生修道院第二学期始業式御教話
石田秀夫先生筆録
昭和十年九月某日
新学期始業式に当って、五項目の事を簡単に話してみたい。
(第一)身体の健康
「汝らは神の宮なり」(コリント前3-16)
「人(が)もし神の宮を毀たば、神(は)かれ(=その当人)を毀ち給はん」(同-17)一
「みづから(を)害ふな」(使徒16-28)
己の身体は、もとより己一人の所有物ではない。神の宿り給う神聖な宮である。単なる運動器官ではなく、もっと精神的なものである。この考えがないと健康問題は徹底しない。特に体の基本が作られる青年時代には、よく考えねばならぬ。ここ(=学生修道院)に入った人は、玄米食にとまどうであろうが、この道の第一人者・二木謙三博士(=日本伝染病学会初代会長。文化勲章受章者)の指導を受けているので、安心して実行されるとよい。博士には近々お願いして、講話をして頂こうと思っている。
昔はこういう科学的な健康法の考えが無かったため、可惜(=惜しくも)短命で終わってしまった人が多い。今日はその中、二人ほどを例に挙げておきたい。こういう人がもう少しでも長生きしてくれたら、どれだけ日本のためになったか知れない。
その一人は山岡静山という人である(=高橋泥舟の実兄。後述の山岡鉄舟の義兄)。幕府の旗本で、槍の名手、早くも二十代で日本第一の名人と謳われていた。凡人には真似できないような苦労を積み、毎日三千回もの稽古を欠かさなかったという。唯一、九州の方の名人(=南里紀介)と試合をして、勝負がつかなかったが、それ以外には敵する者がなかった。
およそ武芸は技の勝負だと思われがちであるが、静山は技を極めた後、真の勝負はむしろ徳(=精神力・胆力)にあると考え、「人に勝たんとすれば先ず徳を修めねばならぬ。こちらの徳が修まれば、相手は自然に屈服する。それが真の戦いであって、技で勝つ事は真の勝利ではない。最も慎むべきは傲りである。傲慢の心が一たび生ずれば、百芸(も)みな廃る」と考えた。私も昔の事を考えると、冷汗の出る思いである。
その静山が脚気に罹った。脚気は白米による中毒(=ビタミン不足)だとされる。けれども昔の事であるから、それがわからない。
そうこうするうち、騒動が起こった。彼の師匠の反対派に善くない連中がいて、隅田川での競泳を申し入れて来た。武術では敵わぬから、水中に誘って謀殺しようという魂胆(=策略)である。それを聞いた静山は、師匠の恩義を思って駆け付けたが、水に入るや、たちまち心臓麻痺を起し、二十七歳で死んでしまった。もしこんな人物が五十歳、六十歳まで生きていたら、武道界は言うに及ばず、日本社会にどんな薫風(=善い影響)をもたらしていたか知れない。
いま一人は山岡鉄舟(=幕末の幕臣。勝海舟を援けて江戸無血開城に奔走。剣・禅・書に優れる)である。この人は本名・小野鉄太郎といったが、やはり静山の人物に敬服して、二十歳の時に槍の師匠として師事したのである。ところが静山の妹に、十七歳の英子という人があり、懇望されて師匠の山岡家を継ぐ事になった(=静山の実弟・泥舟は既に高橋家に養子に出ていた)。
鉄舟はもともと天下無双の酒豪として通っており、水戸の方の豪傑と飲み比べをした時は、相手は五升飲んで倒れてしまったが、鉄舟は七升飲んでもなお、しっかりした足取りで帰って行ったという。後に西郷隆盛が明治天皇の養育係として選んだだけあって、ただの豪傑とは違うところがあったのであろう。しかし、安倍川餅を百八個食べたとか、茹で卵を九十七個食べたとかいう伝説も残っている。そんな無茶をした結果、三十四、五歳の時、わき腹に塊ができて、千葉立造(=鉄舟の侍医)が診察したところ、胃癌であるとわかった。それからは写経などしながら、病気に囚われず平然と過ごしたという。
「お医者さん、胃癌胃癌と申せども、胃癌中にも善きところあり」
などと詠っていたが、遂に五十三歳で死んだ。辞世の句は
「腹張って苦しき中に明烏」
二人とも国家的に惜しい人物であったのに、医学的知識が不充分だったため、あたら(=惜しい事に)早すぎる死を遂げてしまった。
斯く言う私も、仙台時代は毎晩五時頃から、町はずれ(=宮城野原)の練兵場に出掛けて行き、夜中の一時、二時まで端坐し、冬は鳥打帽の上から風呂敷三枚を被り、赤毛布に包まって瞑想した。若かったので風邪も引かなかったが、後年、呼吸器に支障を来たす事が多くなった。当時、高等部にいた土居という人は、雪の上に毛布を敷いて座禅をし、肺炎に罹って死んでしまった。いくら熱心でも、命を縮めるような修業は為にならぬ。むろん暴飲暴食など、もっての他である。
(第二)忠言
人の忠言(=忠告)は感謝して聞かねばならぬ。二
「忠言を聞けば即ち拝し(=頭を下げて感謝する)、過ち有るを告げらるれば即ち喜ぶ。聖賢に非ずんば能わず」(李邦献)
凡夫(=凡庸な人間)はなかなかそうはいかず、すぐ腹を立てたり、悔しがったりして、せっかくの忠言を役立てる事ができない。
先ほどの鉄舟などは、人が世辞を言うと、むしろ不機嫌になって、黙ってその人の顔を見返していたと言う。千葉立造は精神上、鉄舟の弟子を自認していたので、日頃から師に直言して止まなかった。ある時など、軸物の箱書きを頼まれた鉄舟が、酒を飲んで書いているうち、一字書き間違えてしまった。すると千葉は、「字を間違えるほど飲んではなりませぬ。そもそも酒は胃に良くないではありませんか」と叱り、その旨を箱の裏に書き付けて、それを谷中(=東京台東区)の全生庵(=鉄舟建立になる寺。その禅弟子・三遊亭円朝遺愛の幽霊画50幅を所蔵する事でも有名)に納めたが、後、火事のため焼失したという。
また、鉄舟がある事件に関して過激な意見書を認めたのを見て、「一たん書いた文書は後々まで残るものでありますから、感情に走って書くべきものではありませぬ」と言うと、鉄舟はじっと千葉の顔を見て、「よくぞ言ってくれた。貴公は本当に神様か、仏様か」と言い、改めて書き直したという。先ほどの李邦献の言葉(=「苦言を喜ぶ、云々」)程度の境地には入っていた事がわかる。
先ほどの静山は《傲》を戒めた。傲慢の心があると、人に担がれて足をすくわれる。故に忠言は喜んで聞くようにしなければならぬ。
私が今回会った婦人の中に、相当に弁の立つ人があったが、その人が言うには、「自分を叱ってくれる人は有難い。不親切な人は、相手に好く思われたいがため、なかなか直言してくれませぬ。忠言は親切心がないと言えないもので、その親切から出たせっかくの言葉を聞けぬようでは、進歩などないものです」と。
私も真の人を造りたいから叱りもする。学生の百人や二百人に、悪く言われようと善く言われようと問題ではない。今までに二万人の人を教えて来たが、善い事を言い切る人は滅多にいないものである。
(第三)正義と良心
「聖靈をけがす者は、永遠に赦されず、永遠の罪に定めらるべし」(マルコ3-29)
聖霊は良心の上に位して、良心に命令するものであるから、良心に叛く人は聖霊に叛く事になる。良心の満足は正義を実行する事にあり、善い事をすれば良心が喜ぶ。
ところが日常、この良心が鈍っている事が多い。普段はそれでも誤魔化せるが、いよいよ死ぬ際ともなれば、良心が非常に咎められる事になる。
米国のある人が、子供の頃、人の畑の西瓜を盗んで食った。大した金額でもないので、そのまま忘れていたが、後年、ふとした事から大病に罹り、病床に就いてから急にその事が思い出され、良心が痛んで仕方がない。思い余って、苦しい息の下で詫び状を認め、家の者に頼んで為替(=現金化できる証書)を同封して送ってもらい、それで少し安んじて他界したという。
良心が満足して死ぬのが天国であり、良心に咎められて死ぬのが地獄である。ゆえに日々正義を愛し、聖霊を喜ばしめるように生きる事が大切である。かの孟子も、正しい行ないを積んで四十年、ようやく《天地正大の気(=浩然の気)》(孟子・公孫丑上)に立つ事を得たのである。
(第四)寛恕と徳望
「生涯守り行なうべき一語というものがありましょうか」と子貢(=孔子の高弟)が問うたのに対して、孔子は「それ(は)恕(=人を思い遣る心)か。己の欲せざるところは、人に施すこと勿れ」と答えた(論語・衛霊公)。自分が嫌な事は人にもしない。そういう人に徳望(=徳による人望)は自然について来る。ところが凡人はそうでない。悪口を言われて喜ぶ人などいない筈なのに、平気で人の悪口を言うのである。
私が仙台にいた頃、「東北三大人物」なるものがあった。押川方義(=東北学院創設者)、南天棒(=松島瑞巌寺住職)、乃木希典(=当時は仙台第2師団の若き師団長)である。
押川先生については、波多野鶴吉翁(=郡是創業者)などが、「先生の前に出ると、自分まで大きく拡張されるような気がする」と言っていた。この押川先生が《英雄》とすれば、南天棒は《豪傑》くらいである。
私は南天棒の所にもよく行ったが、コセコセするのが嫌いな、広々とした愉快な人であった。ある時、師団の大隊長(=児玉源太郎)が教えを請いに来ると、「お前は隊長さんだそうだが、一つここで隊を指揮して見せろ」と言った。躊躇していると、やおらその人をねじ伏せ、馬乗りになって尻を叩き、「大隊、進め!」と言った。大隊長はすっかり恐れ入って、直ちに弟子入りしたという。酒などは摺鉢に注いで飲み干すという酒豪で、私も一緒に飲んだ事がある。物外和尚(=幕末の曹洞僧。拳骨和尚で知られる)の事を話したら、「あれは力禅じゃ」と言い、釈宗演(=鎌倉円覚寺・建長寺管長)については、「才子禅じゃ」と切り捨てた。若い私は、そんな和尚に惹かれて、つい自分もいっぱしの豪傑になったような気持になり掛かった。
宗教で悟って、わざと人を罵倒したりする事を《機鋒(=刀の切っ先・言葉の鋭さ)》と言うが、それを戒めた言葉がある。
「機を弄すること勿れ、機を弄すれば徳を損ず」(出典不詳)と。
たとえ自分がどんなに明快に悟ったとしても、一方で人の悪口など言わないのが徳というものである。
南天棒は九州(久留米)の梅林寺で猛烈に修行して悟った。六年間というもの、横になって寝た事がなく、眠くなると手の甲を棒で打って眠気を払った。それで武道家のように手に胼胝ができていたという。それだけ修練した人でありながら、徳を欠いたので、ついに妙心寺派の管長にはなれなかった。いくら力があっても、徳望が無ければ人は集まらない。ましてや、力もないのに人を悪く言うようでは話にならない。
(第五)敬虔厳粛
「自ら敬虔を修業せよ」(テモテ前4-7)とパウロも言っている。
今や秋、秋の気候は人の精神を敬虔厳粛にさせる。どうか諸君もこの精神を修めて、前述の四項目を実行・統一するよう努められたい。
ヒマラヤの高峰であれ、地球全体であれ、それを統一しておられるのは神である。その神の前には、孔子も基督も敬虔の精神でもって、「天に在す神」と称えておられる。それくらい厳粛な存在なのである。
人は宇宙を呑むような精神になって、初めて世界的な人物になれる。それには、ただ人と比べて得意になったり、嫉んだりしているようではいけない。日夜、神と生きた交通ができるようにならねばならぬ。それには生きた信仰を持つ事が不可欠なのである。
学生修道院夕食後のご教話
昭和十年五月二十一日
多くの人が安逸を求めるが、安逸は求めて得られるものではない。そもそも学生時代から安逸など求めていると、勉学が大儀(=めんどう)になる。むしろこの時代にこそ刻苦精励すべきであって、後に偉くなったような人はみな、若き日に艱難辛苦を厭わず求め続けた人である。
支那(=中国)の名僧に慈明という人があって、「西河の獅子」と言われた。酷寒の時期に皆が修業を休むのを後目に、朝夕務めを怠らず、眠気を催すと錐で自らを突き刺したという。白隠はこれを『禅関策進(=禅僧の苦行伝)』で読み、非常に感動して修業に励んだ。その結果、「五百年間出の宗匠(=500年に1人出るか出ないかの大師匠)」と謳われるまでになったのである。
古人はそのようにして励んだ。それを「都会に出て来たからには都会風にならねば」などと考え、やれ日曜には活動写真(=映画)を見に行くの、やれ親に貰った金でカフェに通うなどしていたのでは、その行く末は目に見えている。仏教の方で《顚倒の見》という言葉がある。足に履くべき靴を頭に頂くような見当違いを言う。ナポレオンは華の都パリに出て来て、学友から故郷コルシカ訛りを笑われたが、そういう連中は相手にせず、もっぱら『プルターク英雄伝(=プルタルコス編の古代英雄列伝)』を読んで修行した。それが後年、世界五大英雄の一人を作る素地(=土台)となったのである。
教訓集第一巻より
新入社員講習会訓辞
大正十五年四月十日
まずこの会社の精神と教育法は、世間の学校のそれとは異なっている事を承知されたい。世人は近来、学校教育に欠陥を感じて、体験とか実践とかいう事を言い出した。すなわち知識を理解しただけでは役立たず、理解したものを体得・実行する事を要するのである。これからお話しする事も、頭ではわかり切った事であるが、いざ実行するとなると、なかなか容易ではないのである。しかもただ諸君が会社にいる間だけではなく、終生踏み行なって行くべき事柄なのである。
およそ道の修行というものは、名僧と言われた人でさえ、二十年、三十年、四十年と骨折ったものである。その代わり、そうやって得たものは、たとえ天下が挙って反対してもびくともしないのである。頑固で動かないのではない、確信して揺るがないのである。この精神が当社を動かしている。それはいくら頭で考えてもわからず、悟って初めて至り得る境地なのである。
(一)誠実
誠実が根本である。当社で毎月末に精勤賞として出している手拭に、「至誠(=誠実の極み)は万事の基なり」と染めてあるが、これは十八年前、前社長の求めによって私が書いたものである。人格を練るにも、学問するにも、研究するにも、天地一杯に充満したこの誠の精神を以て当たるのである。
どこまでも真理を探究して止まぬ誠実の精神は、西洋では学問する人の心に働いており、東洋では宗教家の心に働いている。日本人は西洋の学問を取り入れるに熱心であるが、その根本たる誠の精神を採っていない。ゆえに表面的な借り物に終わってしまう。当社はこの誠を会社の根本生命としているのである。
生命であるから、理解してそれで可しというものではない。誠は一生懸命の働きの先に見えて来るものである。古の孝子が親の病気を治したいと、寒中に水垢離するあの誠心である。
釈迦は摩伽陀国の浄飯王の王子であり、三昧殿という美麗なる宮殿に住み、妃は才色兼備の耶輸陀羅姫、二人の間には一子・羅睺羅まであって、人生の富貴歓楽を一身に集めていたのであるが、それら全ての愛着を抛擲(=投げ捨てる)して、「我もし正覚を遂げずんば、誓ってこの座を立たず」との精神で以て修業に入った。ソクラテース、マホメットもまたそういう精神で立った。
この誠心があれば、二心なく純一になれる。それを「妻子が可愛いから」とか、「男一匹、有てる力を試してみよう」などと、よそ見ばかりしているから純一になれない。諸君はこの会社にいるのであれば、会社を信じ、社訓を守って他を思うべきでない。今も今で、この講義に一心・純一にならねばならぬ。私も今は心中に諸君あるのみ、神も国家も天も地もない。而してまた神の事を思う時には、神の他に一切何もないのである。
然らば誠とは何か。それは「古今に通じて謬まらず、中外に施して悖らず(=間違いがない)」(教育勅語)と仰せられた永久不滅の道である。諸君は他日(=将来)、当社の幹部となって働く人たちである。その時、この誠を体現していなければ、決して人は服さない。まさに「十目の視る所、十手の指す所、それ厳(=厳格)なるかな」(大学)である。これは私の十八年間の教育の結論でもある。
誠でさえあれば、たとえ愚鈍に見えても、結局は信ぜられる。孔子は曾参を、「参や魯なり(=曾参は愚かで鈍い)」(論語・先進)と評したが、他ならぬその曾参が孔子の道を継承したのである(=『大学』を講述し、『孝経』を編集し、その学問を子思[=孔子の孫、『中庸』他の編者]に伝えたとされる)。
世智弁聡(=世知に長けて小賢しい事。「仏道八難」の一)は悟道の妨げとされる。木戸孝允は、「才子は才を恃み、愚は愚を守る。少年の才子は愚に如かず(=才ある者は才に頼り、愚者は愚直に徹する。若き日は才子たるより愚直なるがよい)」(偶成)
と言った。土を見て土と知るのは才智である。土を見て井戸を掘ろうと思い立つのが立志である。しかし孔子の水脈、釈迦の活泉は共に深い。ゆえに堅い覚悟を以て、実践躬行(=実際に自ら行なう)しなければ達しない。
(二)謙遜
謙遜も実践するとなるとなかなか難しい。謙遜の極みは虚心・無我である。すなわち我を無にし、心を空にするのである。
外部から郡是へ入って来た人は、どうしても自分の過去の経験の物差しで測るから、なかなかわからない。法律を修めた人は法に縛られ、学問を積んだ人は学問に捕われ、修業した人は修業に泥む(=拘泥する)。いかなる学問があろうと、いかなる知識があろうと、一切捨てて掛からねば入れない。
古人は謙遜の徳を積む事に非常に苦心した。張良(=劉邦を援けて前漢を創始した功臣)は「容貌は婦人の如し」と太史公(=『史記』を著わした司馬遷)が記しているが、若い頃はなかなか気性の激しい人であった。秦の始皇帝を暗殺しようと、力士を雇って、百二十斤(=30kg)の鉄槌を皇帝の馬車めがけて投げ付けさせたが、護衛の車に当って失敗に終わった。
それから命辛々、下邳まで逃げ伸び、坏上(=石橋の上)で黄石公という不思議な老人に出会った。老人は履いていた鞋をわざと水に落として、「拾って来い」と命じる。「何様の積りか」と腹を立てたが、何しろ追われている身でもあり、ここで事を荒立ててはまずいと思って言われたとおりにすると、「孺子(=若造ながら)教うべし。五日後、また此処に来い」と言う。言われた日に行くと、老人が待っていて、「年長者を待たせるとは礼儀を知らぬ奴だ」と叱りつけ、「五日後にまた来い」と言う。今度は夜明けを待って行くと、すでに老人は来ていて、「駄目だ、もっと早く来い」と言う。「ならば」と、前日の夜から待ち続けて漸く老人に会えた。そして『太公望兵書』というものを手渡され、「これをよく学べば、帝王の軍師ともなれようぞ」と言われた。
猛勉強した張良は劉邦に見出だされ、その結果、かつて武力で倒せなかった秦を、智略でもって滅ぼす事に成功し、前漢四百年の大いなる基を扶植(=助け立てる)するに到った。
こうして功成り名を遂げた後は、「山の麓で黄色い石を見つけたら、それを儂じゃと思え」と言い残して去った老人(=前述の黄石公)の遺言を守って、穏やかな晩年を全うしたという。血気盛んであった若者が、謙遜を学んだ結果である。
(三)感恩
人天の恩を感じないような人は、そもそも心が美しくない。およそ天地の恩を感じないようでは、人として失格である。大気、光熱、風水、みな天の恵みである。また周囲からも日々、有形無形の恩恵を蒙っている。親の恩、師の恩、家族の恩、上司・部下の恩等々、みなそうである。自力だけで世が渡れると思ったら、甚だ浅薄である。社会の根本改革も感恩の心から起こる。労働問題・思想問題もこれで自然解決する。
大事業も感恩の心より成る。法然(=浄土宗開祖)、親鸞(=浄土真宗開祖)、ルーテル(=新教開祖)の改革もみな、神の恩を謝する篤い心から生まれた。日本国家の恩恵も、内地にいたのでは気づかないが、支那(=中国)など治安の乱れた国へ行くと、故国の実力というものが実感される。個人が護身する以上に、母国が守ってくれているのである。それを自分の力だと思い上がってはならない。それは会社という組織に身を置く者にもよくわかるであろう。若い人でも世間で侮られないのは、後ろに郡是が控えているからである。
(四)公義
基督は「まづ神の國とその義しき(=公義)を求めよ。然らば此等のもの(=衣食住)は皆なんぢらに加へらるべし」(マタイ6-33明治訳)と言われた。私の四十年間の経験から言っても、全くそのとおりである。出処進退(=就任・退任など身の処し方)みな公義に由らねばならない。公義に外れて、名利などが入るとたちまち醜態を晒す事になる。
ロシアから金品を貰って赤化思想(=社会主義・共産主義)を喧伝し、アメリカから裏金を得て共和思想を吹聴するなど以ての外である。そういう者は自分の信奉する国に籍を移せばよい。私利私欲のために公義を忘れ、自分の国を売るなど断じて許さるべきでない。
同じくまた、この会社に入ったからには、この会社の精神に従うのが当然である。どうしても気に喰わないなら、速やかに去るべきである。私など、明日の米が無い時でも、地位に恋々たる事は一度もなかった。粥を薄めて凌いだ日々もあるが、それでも俯仰天地に愧ずる所はなかった。
入社する際にはいろいろ誓い、懇願までして入って来て、入ってからあれこれ不平を言うのは卑怯である。私は十四歳の時、絵入り『三国志』を読んで関羽の人となりに打たれた。かの近藤勇もこれを読んで泣いたという。近藤は関羽の公義の心によって、荒くれどもを統率して行ったのである。
その関羽が麦城に囲まれて、敵方から降伏を勧告された時、
「我はもと解梁の武夫。漢中王(=劉備玄徳)と誓を結んで、恩を受くること身に余れり。あに義に背いて敵に降らんや。城もし破れば、快く討死せん。(・・・・)玉は砕けてもその白きを改めず、竹は焚けてもその節を毀わず、人は死しても名を失わず」
と返答した。我々もこの精神さえ持てば、世を隔てて(=時空を超えて)関羽と一になる。出処進退、何ぞ逡巡(=ためらい)あらんや。
(五)勤労
禅家の方で、「五百年間出(=五百年に一人の逸材)」と謳われた原の白隠(=江戸中期
の臨済僧。原は旧東海道宿場町の一つ)が、四十年の修行によって得た《勤》の意義は、
「天下の英雄、古今の豪傑(は)、みなこの一字より出頭(=頭角を現す)し来たる」
というものであった。
《凡人》とは読んで字の如く《人並みの人間》である。そこから嶄然と(=一段高く)他に抜きん出るのが偉人である。世に凡人は多く、偉人は少ない。《勤》の一字を勉めないからである。
「君子はその位に素して行ない、その外を願わず(=君子は己の置かれた境遇に応じて身を処し、それ以外を望まない)。富貴に素しては富貴に行ない、貧賤に素しては貧賤に行ない、夷狄に素しては夷狄に行ない(=未開の地にあれば未開の人らしく振舞い)、患難に素しては患難に行なう。君子は入るとして自得せざることなし(=君子たる者、いかなる境遇に置かれようと、必ず自ら充足するものである)」(中庸)
君子は貧賤・不自由・患難に直面しても乱れる事がない。
現今、「上流階級が働かないなら、無産階級もまた働かぬ」などと言い出すのは愚の骨頂で、せっかく与えられた勤労の尊さを知らぬ者の言う事である。今の国情は、ちょうど貧乏人の夫婦喧嘩のようなものである。そんな事に現を抜かしている場合ではないのであるが、それを許しているのもまた指導者の罪である。
私は日本を救いたい。勤労の精神で以て人々の人格を高め、民度を高め、国家を高め、世界を救いたいのである。武力ではない。完全の理想に向かって、誠を土台にして進めば、いつか世界は善くなる。遠大な事業であるが、その基礎は身近な教育である。
(六)完全の理想
完全の理想に向かって不断に進む事。それは言うは易く、行なうは難い。私は三十八年間修行して、その二十年目にこの会社に来た。この会社は「良き地」の畑(マタイ13-8)であるから、良き種が育つ事と思う。これを世界に広めて、世界を教化すれば、この世に天国が実現する。それには郡是の人が手本となって進まねばならぬ。どうか諸君は世界を変える使命を負っているつもりで、よく体得・実行されん事を望む。
山月先生文集(144)
山月子『女学雑誌』記事(十八)
愛
妙(=絶妙)なるかな、基督の愛、(それは)我らが(=我らの)汚れを洗うて雪の如く清からしめ、花の如く香らしむ。我、時として人に毀られ(=悪口され)、人に誤たる(=誤解される)。困難と悲哀と痛苦、具にこれを甞む(=経験する)。されど我、何ぞ基督の愛を離るるを得ん。何ぞ基督の愛を以て人を愛せざるを得ん。
富により、智により、義によりて、何事をも成し得べしと考えし頃の我(は)、真に及ばざりけり。人を教え、人を救い、人を助けんと思いし頃の我(は)、《彼我(=自他)》の思いの抜けずして、実に至らざりけり。愛よ、汝は我に人生の秘義を悟らしめたり。ああ神は即ち愛なり。我に愛ある時は、即ち神が我に在す時なり。我(が)、愛もて働く時は、即ち神が我に在りて働き給う時なり。自ら働かずして神が働く時、何ぞ自ら義なりなどと思わん(=どうして自分を正義の人間などと考えるだろうか)。なんぞ自ら教うる・救う・助くるなどと考えん。やむを得ずしてこれを言行に発せしのみ。義と思わずして義、忠と思わずして忠、孝と思わずして孝、信と思わずして信、全ての善事は愛の結ぶところの実(=果実・成果)なること、ああ我は真にこれを知る。
悠々として独り頭を挙ぐれば、喜悦の微笑(は)面(=顔)に溢る。讃美すべきかな基督の愛、而してこれを我に知らしめし人こそ、真に感謝すべきなれ。我は永遠に、未来までも、その人の徳(=厚意)を忘れざるべし。
ヨハネ曰く「未だ神を見し者なし、我等もし互いに相愛せば、神、我等の衷に居たまいて、彼を愛する愛を我等の衷に完全す」(ヨハネ1書4-12明治訳)と。ソロモン(=イスラエル第3代の王、旧約『雅歌』他の作者とされた)歌うて曰く、「愛は大水も消すこと能はず、洪水も溺らすこと能はず。人その家の一切の物をことごとく與へて愛に換ん(=愛を買い取ろう)とするも、尚いやしめらるべし(=軽笑されるだけだろう)」(雅歌8-7)と。
愛は生命なり、永久も堕つることなし。我(は)、愛に連なれば、即ち限りなき生命を得たるなり、永久も堕つることなきなり。紛々たる(=乱れて入り混じった)俗世の毀誉(は)、何ぞ我に関からん(=関係あろうか)。視よ、地上の大雨(が)盆を傾けるが如く、雷鳴轟き、電光閃く時(も)、芙蓉の山巓(=富士の山頂)は凞々として(=穏やかに)日光(が)輝くなり。 (明治25年2月25日 女学生第21号)
桜窓雑感
引(=導入の文)
昨夜、武を演ぜし庭前(=明治女学校では文武両道を尊び、星野天知などは武道も教えていた。彼は後に柳生心眼流第八世を襲名)は掃除全く了りて、桜花(は)旭日(=朝日)に笑う。書窓(より)花に対して(=書斎の窓から花を眺めて)恍乎自失する(=うっとりして我を忘れる)こと暫し。遽然として(=にわかに)自覚し来たれば、情は新たに、感は湧くが如く、筆を下せば、下篇(=以下の文章が)即ち成る。
(一)妄りに批評すること勿れ
我が家は富士の北麓にあり。三ッ峠山と倉見山は家の表裏に聳ゆ。幼時、これを見て思うに、倉見山(が)最も高く、三ッ峠(が)これに次ぎ、富士山は次の次なりと。何ぞ知らん(=どうして知ろうか)、富士こそこれ日本第一の高山、三ッ峠は郡内(=山梨県東部、桂川流域、南・北都留郡の古称)屈指の高嶺(=1785㍍)にして、倉見山は地誌にも載せられざる低山(=1256㍍)なりしこと。
燕雀(=燕や雀)が鴻鵠(=鴻や鵠)の志を知り得ざる(=「燕雀、安んぞ鴻鵠の志を知らんや」[史記])は、まさに真なり。童子は大人の心を知る由もなし。思えば我等もまた、妄りに(=思慮もなく)人を評すべからず。「人を議すること勿れ」(マタイ8-1明治訳)との基督の戒めは、千載(=長い年月)を経るも益々新たに、益々真なるを感ず。世にも憐れむべきは、自ら小なることを悟らずして、妄りに人を評定し去る人なり。我はこれらの人の為に、(憐憫の)熱涙膝を湿すを知らざるなり(=気付かぬほどである)。
(二)弁解
他人を愛し、自分を信ずる人は、他人の為に自分を弁解せんと思うことあり。何となれば、他人が自分を誤解するは、他人にとりて不幸・不利なる事を知ればなり。されど記憶せよ、沈黙こそ最も雄弁な弁解なることを。汝(が)、他(人)を愛し他を憐れまば、他の魂の為に、誠実に神に祈れ。神は自らよりも他を愛する者にあらずや。我等の願い、もし善ならば、如何で(=どうして)神に聴かれざることあらん。
(三)改革家を改革すべし
現今、不適任の自称改革家多し。我等は一層深く養い、高く任じて(=自任して)、世の所謂改革家を改革せざるべからず(=しなければならない)。
(四)当今の人士
当今の人士(=地位・教養のある人の)、多くは余裕なし、薀蓄(=知識・学識の蓄え)なし。一見すればその人の腹中、見え透くが如し。交わること久しうして、美点・長所の次第に顕わるるが如き人物は幾人やある。「見渡せば花も紅葉もなかりけり」(藤原定家)、突進の士卒(=兵卒)はあれども、胆大・寛弘・仁愛の大将なし。古歌に曰く、
「人多き人の中にも人ぞなき。人となれ(=人士たれ)人、人となせ(=人士を育てよ)人」(空海)。
(五)顕と隠
陳勝、呉広(=共に兵を挙げて秦朝滅亡の端を開いた人物)が出た時、天下は項羽(=秦を滅ぼし、楚王となった覇者)の出で来ることを知らず、まして高祖(=項羽を垓下に破って天下を統一、漢王朝を建てた劉邦)の存在など知る由もなし。
小人はただ眼前に顕れた現実のみを見、達観の士は、未だ隠れたる処にその眼光を注ぐ。
(六)宋襄の仁
姑息(=その場しのぎ)の愛・偏小の義は、路傍の乞食を憐れんで銭を恵むことあり。而して艱難の中、貧苦の家、悲哀の境(=境遇)、義人烈女、愛国憂世の志を伸ぶるに由なく(=大志を伸ばしてやる手立ては持たず)、風前月下(=居心地よい時節の美しい光景。ここは風前灯下[=風前の灯火の如く危うい境遇]の誤記か?)に暗涙を飲む(=人知れず涙ぐむ)者あれども、未だかつてこれに対して同情を表し、この為に一掬(=一滴)の涙を注ぐ者あるを聞かず。
三歎す(=繰り返し嘆く)、現今の宗教信者(にして)、宋襄の仁(=宋の襄公は「楚の布陣が整う前に撃つべし」との進言を、「仁に反する」と退け、反って楚に敗れ去った故事から、《無益の情け・場違いな憐れみ》を言う)に似たるもの多きことを。
(七)哀苦と偉人
我等が種々の悲哀と苦痛を蒙るは、(一)には、よく至誠を養い、(二)には、世間多くの苦しみ悲しむ人々に同情を表し、よくこれを慰め、これを導くことを得んが為、我等の心にまずその経験を与え給う神の摂理(=神慮)なり。幾多の人の経験を一身に持つは、即ちその人の偉大なるところなり。故にその苦痛・悲哀の山の如くなるとも(=山のような苦痛・悲哀に見舞われても)、喜び謝して受くべきなり。
(八)円満の愛
「我、愈々爾曹を愛すれば、愈々爾曹に愛せられず、されど喜びて爾曹の霊魂の爲に財を費やし、身を盡すべし」(コリント後12-15明治訳)と記ししパウロの心は如何に美しく、如何に大なるかな。
十字架上に己(=キリスト)を殺す者の為に、「父よ、彼らを赦し給へ、その爲す所を知らざればなり」(ルカ23-34)と祈り給いし基督の心に至りては、我等(は)何の言を以ってこれを讃美すべきやを知らざるなり。ああ我等(は)深くこれを思わば、よく円満の愛を悟ることを得んか。
(九)神の子の伝記
汝は親に対して孝なるか、兄弟に対して愛あるか、朋友に対して信あるか、神を確信して深愛するか、貧困・艱難・悲哀・疾病に、およそ打ち勝つことを得るか、永遠に忍びて神の為・人の為に使わるるか。汝の日々の一言一行は、まさに汝の伝記を書きつつあるなり。努めよ、「神の子の伝記に新たなる一頁を加えんことを」(ウイリアム・ブース)。而して神の子の伝記は善美ならざるべからず(=善美でなければならぬ)。基督曰く、「如此するは、天に在す爾曹の父の子とならん爲なり」(マタイ5-45明治訳)と。
(十)基督を讃美す
「此の時イエス、心に喜びて曰ひけるは、天地の主なる父よ、此の事を智者と達者とに隠して、赤子に顕し給ふ事を謝す。父よ然り、これ是の如は聖旨に適へるなり」(同11-25~26)。
ああ主は今も在せり。当時の弟子に喜び給いたれば、今の弟子たる我の、一事を悟れることに於いても、深く喜び給うものと信ず。これを思えば、感謝喜悦の念、自ら禁ずること能わざるなり。ああ我もし讃美せずんば、「石まさに叫ぶべし」(ハバクク2-11)。
(明治25年3月22日 女学生第22号)
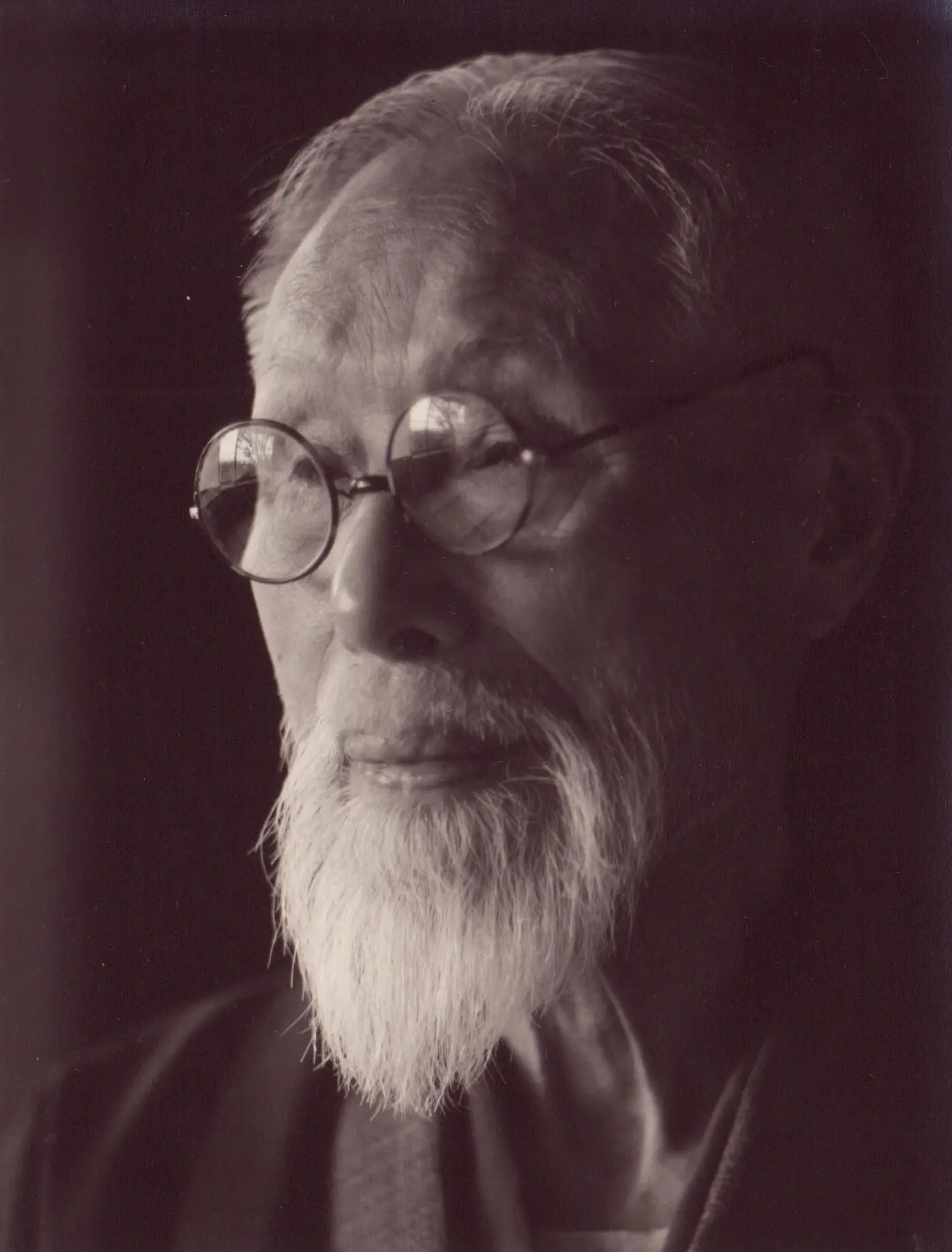

コメント