基督の心第三一〇集
山月御教話・続編(十六) 石田秀夫先生筆録
郡是(グンゼ)本宮(もとみや)工場主任会ご教話
昭和十一年五月十五日朝
会社のような組織体においては、何よりも上下各部の協力一致が大切であり、それに関する質問もよく受けるのである。社員や幹部の統一が取れなかったりすると、社長・場長は己の不徳(=不行き届き)に帰する事になるので、悩んだ末に質問に来るのである。
それは団体を纏める人に共通した悩みであるが、小手先の方策などでは到底凌げない。やはり根本は信仰問題なのである。
およそこの天地の生ずる以前から、至善なる大精神(=神意)が遍在(=遍満)していて、ある時、ついに時到って万物を造化発育させ、人間を創生育成した。その上で、(自らの創造物を)昔も、今も、そして未来永劫、見守り続けているのである。それを神の《道徳性》と言い、古人は《道》とか《真理》とか名づけて来た。教育勅語にも「古今に通じて謬らず(=過去・現在に照らして誤りがなく)、中外に施して悖らず(=国内外に実践して道理に反するところがない)」と言ってある。
この信仰が修まらぬ限り、内心の統一も、団体の統一も付かない。人を統一しようとすれば、まず自分が統一されていなくてはならない。天地一杯の神と繋がっていない限り、人の心は善と悪の間を揺れ動いて止まない。すなわち信仰・修養と教育・訓練が一つになっていなければならないのである。
上に立つ者は、誰からも見られる。下にいた時なら問題にもならなかったことが、上に立てば、嫌でも目立つようになる。ゆえにそれまで以上に身を正さねばならない。ところが人の耳目ならともかく、天地一杯の神の眼・神の耳を相手にする時、一体どう取り繕えばよいのか。それを考えれば、否応なく心が変わって来る。例えて言うなら、監視係に見張られて働いていた工員が、神の前に働くという気持に目覚めた時には、もはや監督など不要になるのと同じである。
西洋などでは古くから基督教の伝統があって、《天職》の観念が行き渡っており、職工自身が良心の監督者になっている。私どもも信仰によって人格を大きくしていかねばならない。人は草木と同じで、成長が止まればすぐ朽ち始める。いくら書物を読んでも、それによって育つことがないなら、単なる記憶の集積、活きた本箱、世に言う「本の虫」で終わる。物事をよく咀嚼(=噛み砕く)して役立てるのが修養である。
福島の片田舎の巡査の細君(=妻)が、覚えたての平仮名で聖書を読み、「旅人を懇ろに待せ」(ロマ12-13)と書いてある所を読んで感心し、夫の上役・同僚・部下に、隔てなく親切にした。すると夫の評価が上がって、どんどん出世したという。私の話を聞き慣れて、一向に実行しない幹部よりも、初めて聞いて、「なるほど」と感じて実行する職工の方が、ずっと進歩が速いことがある。
信仰・修養の心がないと、忍耐ができず、継続して進むことができない。昔の立派な人はみな、困難を克服して進んだ。それを見習って己の人格を作っていくことが大事である。
西郷隆盛の子息(=西郷菊次郎氏)が京都市長をしていた。私は会って話したことがある。西南戦争で片足を失くし、顔は(父に)似ていないが、親切な人であった。その語る所によると、西郷は沖永良部島に流された上、牢に入れられたので、精神的抑圧と運動不足とから、あんなに太ってしまったのだという。誰も見ていない牢の中で端坐・黙想して、日々考えたのであろう。内には火のような感情と、断行の勇を持ちつつ、焦らず、悲観せず、じっと堪えて、天命に従い、藩侯(=島津斉彬・久光)に従順の精神を持ち、人格を鍛錬し、天地と共に鎮まる(=取り乱さない)方面を養っていったのである。
若い時は短気であったが、利き腕を負傷したことと、親友・真木和泉らの忠告によって、物に動ぜぬ大器の人間になっていった。修養する事によって、欠点が特徴を養っていくことになる。また国家のために尽すには、学問も不可欠である。彼は歴史書を繙いて、時勢を見極める力、適材を適所に使う力などを身に着けていった。
歴史を作る人と作られる人とがある。英雄は歴史を作る。工場にもそれぞれ歴史がある。どうか諸君は修養を積んで、この本宮工場の歴史を作っていく人になって貰いたい。善い事を競うのは善いことであって、パウロはそれをオリンピックの競走に譬えた(コリント前9-24他)。
〇精神を大きくし、誠を充実させること
己の器を大きくし、品質を善くするよう努める。大器であっても品質の悪い者は《奸雄》と貶められる。器には大小あっても、品質は努力次第で幾らでも善くなり得る。
〇力を養う
修業し、実行し、力を養っていく。己の実力は他人の実力を生み、己の実行は他人の実行を生む。無線電信のように、個人が実行する事が工場全体に伝わる。この工場が実行する事が郡是全体に影響する。
どうかこのことを経験して、一人一人が大きくなっていって貰いたいと思う。
教育課教師送別会ご訓話
昭和〇年八月二十八日
「我らは神の中に生き、動きまた在るなり」(使徒17-28)
信仰に入ってから四十年、経験を積めば積むほど、なおもその深さを悟るものである。本日午前三時、(私は)限りなき生命というものを、以前にも勝って悟った。(真の生命は)広さにおいても、深さにおいても、時間においても、限りなきものであるという事が、よくわかった。
我々はなぜ存在し、なぜ生き、なぜ活動しているのか。それを考える時、神によって自分が在ることを知る。凡ては神によるのであって、一分一秒の間も、神と離れることなどできない。これを考える時、学院(=郡是誠修学院)の精神を(退職後も、社外において)継承する事ができる。継承して進み、神より育てられた道徳的・宗教的生命を以て新しい社会に入り、自分が入る事によって社会を清くすることが使命であることを自覚する。
これ(=当社の精神)を適用する時には、謙遜と柔和と愛と従順を以てしなければならない。行なうにも言葉よりも実行を以てしなければならない。
一方、後に残る者は、後任の人とどうして協力していくことができるか。神の生命が一緒に働いてくださることを信じ、自分自身が神によって存在していることを自覚するようにならねばならない。自分の存在が、神を根底にしていることを確認できねばならない。
「父の命ずる所の外、我これを行うこと能はず」(ヨハネ5-19か)
この言葉を徹底して考え、パウロの意識した所を正しく意識せねばならない。神の希望は斯くの如きものであるから、神のご希望に添うようにしなければならない。(退社によって)身体は離れても、精神は神によって常に一体であるから、別れも別れではなくなる。
渋沢(栄一)子爵の孫(=渋沢敬三)が第一銀行で、「銀行を善くすることは方便(=便宜上の手段)に過ぎず、むしろ銀行を利用する者が善くなっていかねばならぬ」と言った。我々も社訓の順序(=「誠を一貫して信仰・人格・勤労・貢献の完全を期す」)を間違えてはならない。
《土台》を一番に考えることが大切である。絶えず進歩する人が、絶えず周囲を引き上げていく。しかも完全を目標にしているから、如何に成績が良くても、謙遜してどこまでも進歩する。
(我々の宗教も)完全を理想としているから、どの宗教をも学んでいくのであるが、あらゆる真理は神から出ているのであるから、決して混濁させられることはない。
先人の説いた所にばかり固着していてはならない。神は我らの上にも、周りにも居給うことを信ずる信仰が大切である。
有形のものを変えようと思えば、まず無形のものを変えていかねばならない。
確固たる自信と絶対の謙遜が大切である。一つ一つ自分が学んでいかねばならない。学ぶことによって、教えることができる、教えることが学ぶことになる。まず己を修め、それによって人を善くしていく。
(逆に言えば)絶えず人格を進歩させるような信仰を、己が持っているかどうか、それが問題なのである。
教訓集第三巻より
日常不断の修養(続き)
大正十五年五月十三日 於 工務主任会
- 人の長所を取る
「取る」とは、学んで自分のものとする事である。
「善を学ぶ者は、人の長(所)を取って短(所)を補う」(呂氏春秋)
これは完全の人格を修めるに必要な修養である。
- 他の短所に染まらず
「朱に交われば赤くなる」(太子少伝箴)
偉人の長所・美点は努力してもなかなか身に付かないのに、短所・欠点は黴菌のように、知らぬ間に感染してしまうものである。プラトーン(=ソクラテ-スの高弟。『イデア論』を説いた)は身体が痀瘻(=猫背)であったが、世人はそこばかり真似た。
白河楽翁(=松平定信。江戸後期の幕府老中)は(寛政の)改革を断行するに当たって起請文を捧げ、「もし業(が)成らずんば、我が生命を召し給え」と祈った。そして先代・田沼意次の政策を廃して、緊縮財政を敷き、風紀を取り締って文武二道を推奨した。ゆえに遊興者・贅沢者・規律を嫌う者からは批判され、蜀山人(=大田南畝。江戸後期の連歌師・戯作者)は、「世の中に蚊ほど(=これほど)煩きものは無し、文武文武と夜も寝られず」
とからかった。そんな事で、せっかくの改革も余り効果を上げられなかった。
この蜀山人はもともと大酒飲みで、見兼ねた弟子たちが禁酒を誓わせた。ところが出入りの魚屋が初鰹を持って来るとたちまち気が緩み、ついに深夜に及ぶ深酒となってしまった。偵察に来た弟子が咎めると、「我が禁酒、破れ衣となりにけり、刺して(=注して)下され、継いで(=注いで)くだされ」と悪びれもせずに詠い、結局禁酒は一生できなかった。
私が二十四歳で東京に出て来た頃、この白河翁の事を雑誌に書いた所、その人物・政策について賛否両論が起こった。先輩はおおむね褒めてくれたが、友人はむしろ蜀山人を面白がった。ところがそんな連中の多くは、今どうなったかわからない。他人の努力を貶し、短所を真似るような生き方は、実際問題として、やはり善くないのである。
「上人は物事を直に見、中人は物事を察し見、下人は物事を曲り見る」(大江重房)
世に下人は多く、中人は少なく、上人は稀である。楽翁は上人に属し、蜀山人は下人に属す。自分自身を見る時、また人の言を聞く時、よく注意すべき言葉である。
- 純一に修養し研究す
純一は頭でわかっても、実際にできなければ意味がない。昔、楚の孫敬という人は読書が好きで、いつも戸を閉ざして本を読み耽っていた。その細君(=奥さん)は働き者で、女手一つで一家の暮らし向きを支えていた。ある日、「穀物を庭に干したまま畑へ行きますから、もし雀が来たら追い払ってください」と、竿を手渡して出て行った。間もなく俄か雨が降り出して、穀物は水に漬かって流れて行ってしまった。細君が帰って見ると、孫敬は竿を手にしたまま、何も知らずに本を読み続けていたという。
ドイツのムンゼン博士(=前出)の純一ぶりは既に話した。
私はかつて東嶺和尚(=白隠禅師の筆頭弟子)の書の中に、「仏祖の言教(は)、一々明了ならざれば措かず(=はっきりさせずには措かぬ」とあるのを読んで疑問を起こし、以来十年間研究した事もある。
- 労苦を厭わず
他人が成果を挙げるのを見て妬んだりしてはいけない。人が成功するにはそれなりの努力や工夫があるのである。それを考えずに、自分は楽をしたまま、結果だけ良くしたいと思っても、そうはいかない。
アレキサンダー大王(=アレクサンドル3世)は世界五大英雄の筆頭である。古代マケドニアの王子に生れ付き、錚々たる名士に就いて学問を修めた。家庭教師はあの有名なアリストテレス、数学はユークリッド(=共にソクラテース門下の世界的大学者)に就いて学んだ。さすがに幾何学は難しかったと見え、「予(=私)は帝王なるぞ。もっと簡便に解ける方法はないのか」と癇癪を起した。するとユークリッドは、「幾何学は宇宙の真理であります。真理を前に帝王も乞食も違いはありませぬ」と窘めた。さすが曲学阿世(=真理を捻じ曲げて世に阿る)の学者などではなかった。
シラー(=18世紀ドイツの文豪)は、「貞操は唯一の至宝にして、皇后の尊きと雖も(=いかに尊貴な皇后陛下であろうとも)、市井の(=庶民の)婦人と(公平な)競争せずば、これを得難し」と言った。
サルバーク(=前出。『完全訓講話改訂版』二四五頁には、18世紀イタリアの名ヴァイオリニスト、ジャルディーニについて同趣旨のエピソードが語られている)が楽器を取って楽壇に立てば、必ず聴衆を恍惚たらしめた。ある人がその妙技の所以を問うと、サルバークは答えて曰く、「一曲を聴衆の前に奏するには、千五百回の練習を要します」と。
全て優れた働きの背後には、斯くの如き労苦の存する事を知らねばならぬ。このような用意と熱心とを以て事に当れば、工務の成績を上げるくらい何でもない。
- 服従の勇志
「雄々しき服従は、真に頂天立地(=広天を頂いて大地に立つ)の独立男子にして、初めてその消息(=奥深い真相)を解(=理解)すべし」(ワーズワース)
現代は反抗的気風が広まっていて、反抗しない者は気弱な人間と見做され兼ねぬ風潮さえあるが、それは本我と私我を混同しているのである。己の立場も弁えずして、むやみに私我を立てるなど、決して雄々しい振る舞いではない。特に団体組織においてはそうである。
人間は決して独力では生きられぬ。早い話、もしこの地球に引力が無かったら、地上のものみな全て、遠心力によって宇宙の彼方へ飛ばされてしまう。引力のお陰で水も空気を地上に留まり、我々人間も地に足を着けて生きておられるのである。この消息を知って神に感謝し、本我を目覚めさせねばならぬ。すなわち天地の真理を知り、それに従って初めて責任ある人間となれるのである。
真に責任感ある人間は、己の不完全を自覚し、独善を慎み、我が儘勝手を押さえ、神に従い、社訓に従って、一致団結、協力一致して職務に励むのである。しかも諸君は職場の主任なのであるから、率先してこの精神を工場内に弘め、相共々に進むよう努めねばならない。それはまさに勇気ある任務であって、臆病では決してできない仕事である。
- 光陰(=時間)を惜しむ
社訓の講習を受けた人は、「時は生命なり」という言葉を覚えているであろう。私も殊に近年になって、この感を強くしている。
「挙頭弾指(=ふと頭を挙げ、無意識に指を弾く間)も嘆息して、須らく(=必ず)寸陰分陰(=一分一秒)の空しく過ぐるを惜しむべし」(道元)
「光陰(を)惜しむべし。空しく雑用心する(=無駄な事に心を用いる)こと勿れ」(大灯)
「道うこと勿れ、老来(=年を取ってから)初めて道を学ばんと。古墳(=古い墓の)多くはこれ少年(=年若い人のもの)」(徒然草)
森田悟由氏(=永平寺第64世貫首)は曹洞宗第一流の大徳(=名僧)であった。一方、本願寺派の村上専精氏(=東京帝国大学インド哲学科の初代教授)は仏教史の大家で、かつて悟由氏に、「各宗の開祖はみな長寿であるのに、道元禅師のみは短命で逝かれて、甚だ悔やまれる」と言ったところ、「いや、早く死んでくれてよかった。長生きされたら、我々のわからない事を一杯遺されて、えらい事になったろう」と答えたという。
この問答からも、道元の偉さと、彼が寸暇を惜しんで著述した事がわかる。無い時間も工夫すれば生まれる。メランヒトン(=16世紀ドイツの人文学者。ルターの思想の体系化に尽力した)の例を見よ。私も歩行の時間・食事の時間・車中の時間を瞑想・祈祷に当てた。群馬県の女学校では、校長と教授と兼ねて事務繁多であったが、廊下を歩く時間・登下校の時間を修養に用いた。やってみると、結構多くの時間が得られるものである。諸君も多忙の中、よく時間を工夫して、日常不断の修養に努められたいものである。
英雄の五大特質
大正15年6月4日 本社職員修養会
昨日までは、もっと別の題でお話しするつもりであったが、今日ふと思い付き、俄かに変更した。それが図らずも社長の(訓辞の)意向とも合致していたようで、不思議の感を懐いている。この話はかつて一度、横浜で講演した事がある。
私共が歴史を読んで、感動と希望と勇気を与えてくれるものは、英雄たちの人格と事業である。もし我々が英雄のような性質を持つならば、事業経営など容易い事であろうし、多数を動かす事も難しくはなくなる。私は英雄の精神特質を研究して三十年になる。今日はその詳細には渉らず、大要を五つばかり挙げて、英雄の本質に迫りたいと思う。これを本当に修めて行ったならば、人を引き上げるにも、事業経営の上にも、大いに益する所がある筈である。
(一)誠実
「英雄の第一特性は至誠なり」(カーライル)
私がここ(=郡是)に来て以来、何十回となく話す事であるが、いくら社訓を諳んじていても、実行が伴わなければ何にもならない。
支那(=中国)三国時代の諸葛孔明(=劉備玄徳の覇業を支えた智将)は、誠実を超えて至誠の人であった。あの『出師表(=出兵を上奏する文書)』を読んで泣かぬ者は人に非ずとまで言われたほどであった。
しかしそんな彼を動かしたものは、他ならぬ主君・劉備の至誠であった。劉備は崩ずる(=崩御する・死ぬ)に臨んで太子・劉禅と孔明とを召して、遺詔(=君王としての遺言)して曰く、「我が子・劉禅よ、この父は不徳にして業半ばにして逝く。朕(=君王の自称・私)亡き後は丞相孔明を父と仰ぎ、全幅これに事えるべし」。孔明に対しては、「もし太子にして佐け得べくんば(=輔佐するに足る人物ならば)、これを支えて漢の政を復興せしめよ。而してその器たらずんば、君(が)自ら国を取れ」と。孔明はその至誠に感泣し、帝の手を取って、太子を輔佐する旨を誓った。
北条早雲(=室町後期の武将、後北条氏の始祖)は戦国の世に出た人で、応仁の乱後の乱世に、己一個の才覚によって今川の客将(=お抱えの武将)となり、遂に小田原を奪って小田原北条家(=後北条氏)の基を開いた。早雲は智者・巧者たるの一方、存外誠実な所があった。その徳を慕って諸方から人が集まって来たのである。
その言に曰く、
「人は陰の勤が肝心なり」と。
今日は『能率論』などが持て囃されているが、目立つ所ばかりを努めても誠は育たない。
秀吉が信長に仕えた頃、今川には優秀な人材がたくさんいた。秀吉はそういう人を味方に引き入れようとあれこれ働き掛けた。その中に大沢次郎左衛門という武将があった。鵜沼城主であったが、秀吉の勧めで降伏し清州城に出頭した。けれども信長は信用せず切腹を申し付ける。秀吉は密かに一刀を与えてこれを逃がした(=その後は柴田勝豊・秀吉・秀次らに仕えた)。信長の短慮と秀吉の誠実とを物語る逸話である。
荒木村重は信長に仕えていたが、(或る)事を以て信長を怨み、伊丹に拠って背いた(=謀反の原因は諸説ある)。秀吉は村重を翻意させようと、単身その城に乗り込んで説得した。この時、村重の部下の者が、「秀吉は供回りを連れておりませんぬ。今これを討てば信長には痛手となりましょう」と説いたが、村重はそれを潔しとせず、そのまま秀吉を帰らせた。これも秀吉の誠実さのなせる業である。
秀吉の話が続くが、越後の雄・上杉景勝は信長と間で次第に反目を強めていた。そんな中、秀吉は景勝に会って直談判しようと、僅か三十八騎を率いて糸魚川の城に向かった。その時、景勝は落水城(=越後勝山城)に行っていて留守であった。そこで景勝の手の者が、「秀吉殿は丸腰で来ております。討つなら今ですぞ」と早馬で知らせた。景勝はこの書状を見て、秀吉の誠意に感じ、「この景勝に疎略あるまじき(=無礼の振舞などあり得ぬ事)を御存じゆえの御出なり」と言って、会談に応じたのであった。
人は誰でも誠実に対しては感動するものである。英雄は努めずしてこの心を持っている。
- 大志
私の所にいろんな人が相談に来る。その多くは、人と衝突したとか、感情を害したとかいう話である。そういう問題は大志を欠き、大局を見ないから起こる。学問があると学問に凝り固まり、才智があれば才智を恃み、文章家は文筆を、弁舌家は弁舌を誇って人を低く見る。それは大志でなく小志というものである。英雄はみな天稟(=生まれつき)に大志を持っているが、我々凡俗は修養してこれを持たねばならぬ。
毛利元就が十二歳で厳島神社に詣でた時の、従者との問答はよく知られているから今は略す。信長が毛利攻めを開始し天正十年には、その元就は既に亡く、輝元(=長男)が家を継ぎ、吉川(元春)、小早川(隆景)二叔(=元就の次男と三男)がこれを輔けていた。
信長は秀吉を派遣するに当たり、「毛利討伐に成功すれば、毛利の領地を全て汝に与える」と言った。秀吉はそれを固辞して、「森(成利)殿、滝川殿、柴田殿の如き宿将(=功労ある名将)でさえ、そのような大賞は受けておられませぬ。もし中国挙がらば(=もし中国地方を平定できれば)、私めはその一歳(=一年分)の収入を頂戴致し、それを以て大艦巨船を造り、朝鮮を攻降し、支那(=中国)に入り、天竺(=インド)を降伏させてご覧に入れます」と言った。「汝、またもや大言するか」と信長は笑ったが、秀吉は後年、実際にその壮図(=壮大な企て)に取り掛かったのであった。
山崎の合戦では、中川清秀(=通称・瀬兵衛)が敵将・斎藤蔵之助を破って、頗る戦功があった。その時、秀吉が轎に乗って通りかかり、「瀬兵衛、骨折り(=ご苦労さん)」と声を掛けた。清秀は、「猿(=秀吉の愛称)め、早や天下を取った気でおるわ」と苦笑いした。秀吉の大志は既に天下を呑んでいたのである。
ナポレオンが一敗地にまみれて(=大敗を喫して)セント・ヘレナ(=南大西洋上の孤島)に流された時、ある人が、「あなたの生涯最良の時はいつでしたか。皇帝即位の時でしたか、華燭の典(=婚礼)の時でしたか」と問うと、「それは世界制覇を志した時だ。雄大の気が天地を震撼させる(=震わせる)ように思われたものだ」と答えた。
英雄には生まれついての覇気がある。我々も小人物ながら、小我を棄てて、英雄の如き大望を懐くべきである。(続く)
山月先生文集(147)
山月子『女学雑誌』記事(二十一)
武芸
吾が祖父(=長州藩武芸指南役)の説なりとて、父上(=蘭方医)の語り給いし言に、
「武は無形なり。撃つに撃たれず、斬るに斬られぬものなり。(・・・・)勇者はその手を刀に触れずして(=刀に手を掛けずに)、よく敵を服さしむ、云々」とあり。
我は思う、かの血気粗暴の輩が他(=相手)を斬らんとて赴き、他が(=相手の)自若(=平然)として動ぜざる風采(=態度)に気を呑まれ、胆(=胆力・気力)を砕かれて、何も成すこと能わざりしというが如きは、蓋し(=恐らく)他が「撃つに撃たれず、斬るに斬られず」という《武》と一なりし(=合一している)が故に非ずや。切言すれば(=端的に言えば)、活きたる武なるが故に非ずや。今、武を習う者(が)、もし《芸(=技術)》のみに留まらば、何の効かあるべき(=何の効果があろうか)。
明治25年4月23日 女学雑誌314号
人物修養(偶感三)
- 読むべきもの
読むべきものは豈(=どうして)書物のみならんや。自らを読むべし、人を読むべし、天地を読むべし。
(二)大なれ
吾人(=我々)の憂うる所は小なるにあり。目を挙げて天地の広大なるを観んかな(=見ようではないか)。吾人(は)この天地を造れる神を信じ、これを愛し、これを信じ、これと一にならんことを欲する者。即ち天地の如き広大なる心を持たざるべからず。
(三)完きを望め
自ら公平なりと信じ、正義なりと任ずる者は愛に乏しく、愛を説き、人情を唱うる者は、毅然(=確乎たるさま)・粛然(=厳かなさま)の精神に乏し。今日の信者は偏僻(=偏り拗ける)の者多し。ああこれ未だ深く基督を愛せざるの故に非ずや。
基督は完全なり。剛く、優しく、大きく、小さく、悠然たり、靄然(=穏やかなさま)たり、毅然たり、粛然たり。真と善と美とはその一身にあり。果たしてよくこれを愛せば、吾人(は)豈(=どうして)化せられざるの理あらんや(=どうして感化されない理由などあろうか)。人々よ、岐路に彷徨する(=分かれ道に迷う)こと勿れ、請う、基督を観よ、完きを望め。
明治24年12月26日 女学生第19号/明治25年4月30日 女学雑誌315号
新著批評
○書法大意(小野鵞境堂氏著)
博文館にて発見するところ、真にその《大意》の名に負かず。もし一本(=この一冊)を机上に備えば、裨補(=助け補う)するところ鮮少ならざるべし(=少なくないであろう)。
○万世之師(金鴎館蔵版)
これ和漢洋の格言を集むるもの。上欄には熟語の詳解あり。既に四集まで発兌(=発行)せり。木版なれば誤字の憂い(=惧れ)も無かるべし。至極重宝の書なり。
明治25年4月30日 女学雑誌315号
新刊雑誌批評
〇国語漢文講義録(吉川半七発行)
中等教育を目的として発行するもの。講義明晰にして遺憾なし(=申し分がない)。且つ質疑応答、懸賞文などあるは、この誌の特色なるべし。
〇城南評論
これ文学の雑誌、屹然として(=すっくと立って屈しないさま)一旗色(=独自の主張)を樹つ。載するところの文、面白きもの多し。
○後進
青年の手に由りて成る。活気鬱勃(=活気盛んなさま)たり。吾人(=我々)は『後進』が義侠の心を発揮すると共に、寛弘偉大の精神を修養せんことを望むものなり。
〇東京批評
政界益々繁忙ならんとする際、『東京批評』は出でたり。国政経緯に通ずるを以って任ずる(=自任する)もの、吾人は発刊の辞を読みて、よくその実を尽さんことを祈る。
〇おだやか
横浜より発行す。基督教青年の手に成る。自任(=自信)の気、紙上に躍々たり。前途有望の雑誌よ、自重なる(=自尊する)べし、謙遜なるべし。
〇呼声
長崎より発行。基督教の雑誌なり。願わくは同地方の光たれ。
〇ぱらだいす
雲州(=出雲地方)松江より出づ。基督教主義の雑誌なり。
〇朝鮮新報
朝鮮の事は、本邦人にして注意せざる者多し。吾人(は)、豈(=どうして)この新紙を紹介せざるを得んや。 明治25年5月7日 女学雑誌316号
文の評
(随感『一村雨』[ひさご筆]の文後に)
山月子曰く、「我この文を読みて、憮然として(=やり切れぬ思いで)涙下る。ああ日本の女子(は)、多くは弱く小さし。未だ真正の偉人を観るの眼識を有せず。而して日本の男子(は)、多くは霊眼なく、純義なし。未だ赤心(=偽りのない心)より淑女を重んずるの精神あらず、これを如何にすべき。
我は確信す、男女の愛をして基督の直接なる洗礼を受けしめずんば(=受洗させなければ)、決してこの状況を救うこと能わずと。
世に軽佻浮薄の男児有り、而して義人(が)これと同じく視られんとす(=同一視されそうになる)。世に不義不節の女子あり、而して淑女(が)これと等しく遇せられんとす。遺恨何ものかこれに如かん(=その遺憾なること何物にも較べ難い)。吾人は天を仰いで、基督の愛の泉が、日本社会を隈なく潤さんことを熱祷する者なり」。
明治25年5月7日 女学雑誌316号
巌本善治氏の慰労会
五月十四日(土曜日)、迎春客(=巌本氏の筆名の1つ)巌本善治氏の慰労会を開きぬ。明治女学校の教員生徒諸氏、孤女学院(=現・滝之川学園の前身。濃尾地震の孤児救済の為に創設された)の大須賀(石井)亮一氏、並びに我が社員等、合して百余名、軽舟四艘に乗じて、牛込より流れ(=外堀と神田川)に随いて隅田川に出で、遡りて向島に着し、松寿園(=鳥料理の料亭。広い庭園があった)に入りたり。
清風(は)翠(=緑樹)を吹きて、麗日(は)躰に快く、談話遊歩(しつつ)また他事を忘れぬ。
日(は)傾き、会(は)散じて、軽舟(は)再び隅田に浮かぶ。時恰も高等商船学校(=現・東京海洋大学)生徒の端艇(=ボート)競漕を観る。喝采の声、水に響きて快し。これ当日(の)期せざるの楽なりき。
巻層雲(は)穏やかに落日を呑み去り、水波は静かにして、舟は既に御茶ノ水の辺にあり。心は澄み、談は熟して愉然快然(=心楽しく愉快なさま)の中、自ずから端然粛然(=落ち着いて心静かなさま)たり。這般の心事(=このような心理状態)を知る者、独り在天の父のみ。
舟は岸に着して、各々家に帰りたり。 明治25年5月21日 女学雑誌318号
問答
〇問 事を成さんと欲するも(その事の長短[=善悪]を問わず)、中途にして気力を失い、加えて何物を見、何物を聞くも愉快を感ぜず。世事、さらに望み無きの感を惹起する事(=引き起こすこと)しばしばあり候。これ如何なる理由にや。この悪魔を退治するの術を併せて御教示くだされたく候。
〇答 物事を成す時、中途にて気力を失うということは、身体の関係もあり。然らずしてただ心の関係のみにてあらば、その事業に対する心の誤れる故なり。否、むしろ人生に対する考えの誤れる故なり。さればこそ、望み無き感をも起こし給うなれ。
人生・人間、これ実に大問題なり。この問題に答えて、吾人(=我々)の霊性を満足せしむるものは基督なり。もし基督を確信することを得ば、望みを得べし、愛を得るべし。基督は言えり、「懼るる勿れ、我すでに世に勝てり」(ヨハネ16-33明治訳)と。
事を厭う者、世を厭う者は、世に負くる者なり。君(が)、未だ基督を信ぜずば、請う、教会に行きて説教を聞き、かつ牧師を訪ねて質問されよ。また既に入門されしおらば、更に確信せらるべし。誠心の熱涙の祈りを以って基督に求め給うべし。
基督は曰く、「求めよ然らば受けん。(・・・・)しかして爾曹の喜び満つべし」(ヨハネ15-7~11明治訳)と。君が世を厭い給うことは幸せなり。そは(=それは)真正の楽に入る門なればなり。君が悲しみに沈み給うことは幸せなり。そは基督の同情を求め得べければなり。ただこの際、最も虚心にして道を求め給うことを要す。
明治25年5月21日 女学雑誌318号
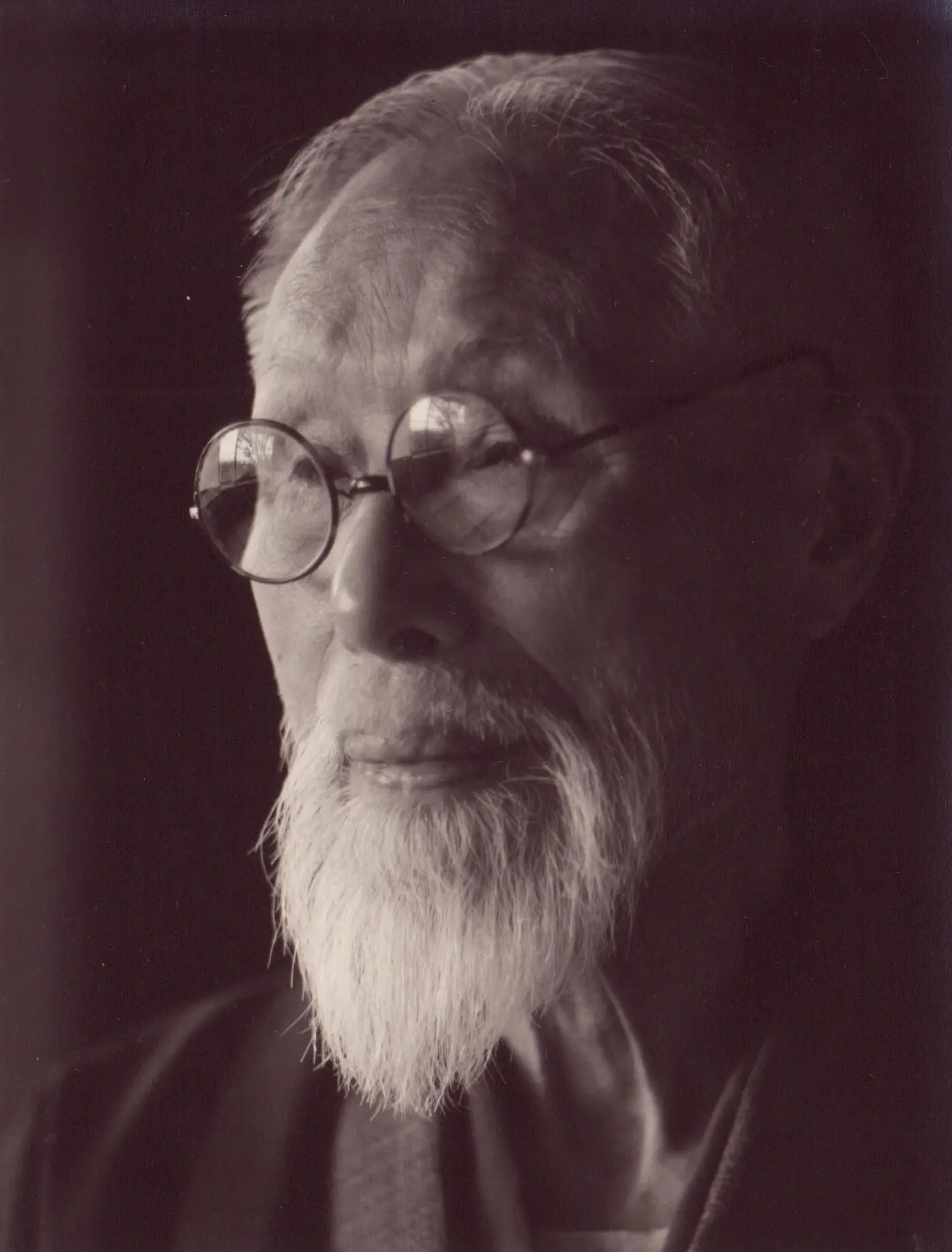
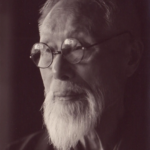
コメント